モン族の人たちは、自分たちの住む家のまわりに麻や綿花を栽培し、糸をつくり、布を織り、
文様を描き、藍に染め、自らの民族衣装をつくっていきます。
モン族の繊維植物栽培と糸づくり

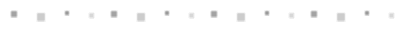
 モン族
モン族の人たちは、家のまわりや畑に、麻や綿花を栽培し、そこから繊維をとり、糸を紡ぎ、布を織り、さらに藍に染め、自分たちの民族衣装などをつくっていきます。
タイ北部のモン族の村周辺の畑には、ちょうど種がはじけ、白い綿花の繊維が顔を出していました(写真左)。
モン族の人たちは、綿布の他に、麻の布もよく使います。麻を栽培し、茎の表皮を裂き、麻布を織るために欠かせない
糸づくりから、自分たちでおこないます。
一枚の布が織り上がるまで、そして、その布に文様を描き、藍色に染め、民族衣装として仕上げられるまでには、長い工程があります。ここでは、ベトナム北部の黒モン族の村での様子を中心にまとめてみました。

民族衣装にしたり、刺繍を刺したりする「布」をつくるためには、切れ目のない
長い糸が必要です。
そのため、麻などから採取した
自然素材の繊維を長くつなぎ合わせる「撚り(より)」の技術が進み、長い糸をつくることができるようになりました。
「長い糸」がつくられるようになったことで、人の「衣」の文化が発展していきました。
麻糸づくりにはまず、麻の表皮を、何本も何本も細く裂いていきます。そして、左手に撚り継ぐ両方の糸の端を互い違いに持ち、その2本を右手の指先の上で、それぞれを同時に手前にころがし、撚りをかけていきます(写真左右下)。このことを、「Z撚り」といいます。
次に、「Z撚り」した2本を重ね合わせ、左手は手前側に、右手は向こう側に指をすべらせ、2本一緒に撚りをかけます。このことを、「S撚り」といいます。
「Z撚り」と「S撚り」を繰り返していくことで、長い糸になっていきます。
撚り継ぐ前の繊維は、左手の甲に巻き、撚り継いだ糸は、左手の指に巻いていきます。
麻は、撚り継いで長くしてから、さらに全体に撚りをかけて、より結合を強くします。
綿花や羊毛など短い繊維の場合は、束にして、糸車で撚り継ぎ、長い糸にしていきます。
天然繊維は、撚りをかけることで、より強く、丈夫な糸になっていきます。

この
撚り継ぎの作業は、とても時間がかかるため、糸づくりの時期になると、子どもからおばあちゃんまで、いつでもどこへでも、麻の繊維を手に巻き、出かけていきます。
写真上の女の子二人は、村から町へ遊びに出かける途中で、おしゃべりしながら、それでも指を休めることなく、歩いていました。そんなところを、ちょっとお邪魔して、撚り継ぎの仕方を見せてもらいました。
町のメインストリートでは、観光客用に布を売りながら(写真左)、市場では、持ち寄った自家製の野菜を売りながら(写真左下)、糸の撚り継ぎに余念がありません。
村の中では、おばあちゃんも、孫たちのお相手をしながら、黙々と撚り継ぎをしています。
糸づくりの時期に、モン族の村や町の中を歩いていると、こうした風景が日常になっています。
モン族の機織りと布

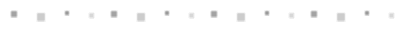
全体に撚りがかけられた糸は、まだ表皮など不純物が付いたままになっているので、灰汁でよく煮て、その後に、土をかぶせておくことでまわりの表皮が取れ、白く、やわらかく機織りが可能な糸になります(精練:せいれん)。
精練前の糸は、緑っぽい茶色っぽい、見た目にも硬そうな糸ですが(写真左下の丸めてある糸)、精練され織られた麻布は、白く輝いた、光沢のある布に織り上がります(写真下)。
この時期は、農作業に忙しい農繁期だったため、機織は分解され、家の軒先や台所などに立てかけられたままになっており、残念ながら、機織りの様子は見ることができませんでしたが、きっと織りの時期には、村のあちこちで、機織りの心地よい音が聞こえてくることでしょう。
モン族のろうけつ藍染め

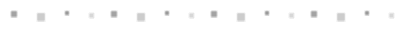

ベトナムの黒モン族やタイの青モン族の人たちは、藍染めした布をつかって、自分たちの民族衣装や赤ちゃんの負ぶい紐やねんねこなどの生活に必要なものをつくります。
いくつかの分派にわかれるモン族の人たちは、民族衣装の色合いによって、「黒モン族」や「青モン族」などと呼び分けられています。「黒モン族」の人たちは、藍染めを何度も何度も繰り返すことでうまれる黒のような濃紺の藍染めの布をつかった衣装を身に付けているため、「黒モン族」と呼ばれています。ここでご紹介している写真は、その「黒モン族」の人たちです。
「青モン族」の人たちは、女性はろうけつ染めの藍染めの布のプリーツスカートをはいています。これは、数回の藍染めの工程を経た、明るい藍色のため、「青」モン族と呼ばれています。
このように、藍染めは、染めを繰り返すごとに、徐々に黒に近い藍色になっていきます。
 ろうけつ染め
ろうけつ染めは、インドネシアではバティックと呼ばれ有名ですが、モン族のろうけつ染めも、手描きの文様に味があり、とてもすてきな布です。その藍染めをした文様の上やまわりに、赤い布などでアップリケすることがよくあります(写真上)。
負ぶい紐用には、四角い布に、ロウ(蝋)で模様を描いていきます。ろうけつ染めは、ロウを置いたところは藍色に染まらず、ロウを取り除いた後に、その部分が白い模様としてあらわれます。
ろうけつ染めにつかうロウは、 蜜蝋(みつろう:ミツバチが巣をつくるために分泌する蝋を精製したもの)、楓蝋(ふうろう:楓の木の幹から樹脂を採り精製したもの)、パラフィン(石油に含まれ分留によって取り出されたもの)などによって模様を描いていきます。
このロウを精製する作業も、大変な時間と労力を必要とするため、最近では市場などでパラフィンを買ってきて使っていることも多くなってきているようです。
ロウを小さなな鍋に入れ(写真左下)、かまどの火にかけ溶かしながら、蝋刀(ろうとう)を使い、かまどの脇で文様を描いていきます(写真左)。
蝋刀は、大小さまざまあり(写真右下)、描く模様によって数種類を使い分け、蝋の落ちる量によって、線の太さに変化をつけて模様を描いていきます。
細い細かい模様を描くときは、小さな蝋刀をつかいますが、中に入るロウが少ないため、何度も何度も蝋刀をロウにつけ、忙しく描いていきます。
モン族の染料づくりと藍染め

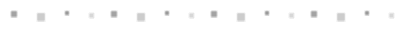
 藍染め
藍染めに必要な染料(泥藍:どろあい)も、家のまわりに栽培した藍の葉(写真右)を採取し、自分たちでつくります。
摘んできた葉を2-3日程度水につけておき、藍の色素インジコになる物質が溶け出してきたところで、葉をすべて取り除きます。
その中に、普段つかっているかまどの木灰を溶かし入れ、よく撹拌(かくはん)していきます。
空気を入れ込むようにすくい上げるようにして、よく撹拌していくと青い泡(藍の華)が立ってきます。その泡が徐々に濃くなっていったところでしばらくおきます。
1日以上おくと、生成された藍の色素(インジゴ)が灰に沈着して沈殿します。その上澄み液を捨て、底に沈殿してできたものが泥藍(どろあい)と呼ばれる、藍染めのもとの染料になります。
こうして時間をかけてでき上がった泥藍で、ろう描きした布を染める準備をしていきます。

泥藍の中に灰汁を入れ、溶かしていき、勢いよくかき回します。そして、時々かき回しながら1-2週間ほどすると、表面に青い泡が立ちはじめ、染められる状態になります。これを、「藍建て(あいだて)」といいます。
いつでも染められるように、一年中藍を建てている家もあり、多くのモン族の家の中で藍樽をみかけます(写真左)。藍は生きものなので、染めない時であっても、時々撹拌して空気を送り込まなければなりません。
ロウで文様を描いた布は、一度水に浸し、藍液に10分程度浸けておきます。取り出すと空気に触れ、徐々に緑っぽい色から藍色に変わっていきます。30分程度したら再度、藍液に浸し、これを好みの色になるまで繰り返します。繰り返すごとに、黒モン族の民族衣装のような黒に近い濃紺になっていきます。
染め終わった布は、熱湯に入れ、ロウを取り除き、よく水洗いして乾燥させ、長い藍染めの作業が終わります。
モン族のピカピカの藍染め布

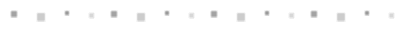

黒モン族の人たちは、藍染めのピカピカの服を好みます。
藍染めの布に光沢をつけるために、家畜の血や卵白を塗るというところもあるようですが、ベトナムで見かけたのは、専用の木製ローラーで布の表面を擦ることで光沢を出す方法でした。
大きなものだと、人が上に乗り、シーソーのようにしながら磨きをかけていくこともあるそうです。
藍染め布にローラーをかけると、藍の粒子が布目を埋め、表面がなめらかになり光沢がでるようになります。
町へ出かける時などは、子どもも大人も、一張羅のピカピカの服を着て出かけます。村から町に遊びに来ていた床屋の順番を待つ子どもたちも、お店のテレビのアニメに夢中な子どもたちも、ピカピカの一張羅の服を着ています。
この日は町中に、ピカピカの藍染めの民族衣装を着たモン族の人たちであふれていました。
ベトナム北部では、まだまだ
モン族伝統の藍染めや織りの文化を見ることができましたが、これから先、どんどん安価な既製品の布や服が入ってきた時に、このモン族伝統の糸づくりや染めの風景や技術は、次第に姿を消していってしまうのだと思います。
それでも、誰かが次の世代へ伝え、残していくことの手助けを、少しでもできたらと思っています。
今はまだ、織り人で扱っている藍染め商品は少ないですが、今後、少しずつみなさまにご紹介していけたらと思っています。
このページの写真および文章を無断で使用することはご遠慮ください。
また、今後の調査研究に基づき、内容を予告なく訂正する場合がございます。

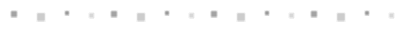
 織り人Topページへ
織り人Topページへ  モン族の民族伝統文化と刺繍ついて
モン族の民族伝統文化と刺繍ついて  ミェン族の民族伝統文化と刺繍について
ミェン族の民族伝統文化と刺繍について
 モン族クロスステッチ刺繍の商品一覧へ
モン族クロスステッチ刺繍の商品一覧へ  モン族リバースアップリケ商品一覧へ
モン族リバースアップリケ商品一覧へ  モン族ライフシーン刺繍商品一覧へ
モン族ライフシーン刺繍商品一覧へ
 ミェン族クロスステッチ刺繍の商品一覧へ
ミェン族クロスステッチ刺繍の商品一覧へ  カレン族手織り布の商品一覧へ
カレン族手織り布の商品一覧へ

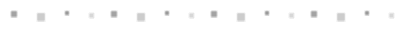

 民族衣装にしたり、刺繍を刺したりする「布」をつくるためには、切れ目のない長い糸が必要です。
民族衣装にしたり、刺繍を刺したりする「布」をつくるためには、切れ目のない長い糸が必要です。

 この撚り継ぎの作業は、とても時間がかかるため、糸づくりの時期になると、子どもからおばあちゃんまで、いつでもどこへでも、麻の繊維を手に巻き、出かけていきます。
この撚り継ぎの作業は、とても時間がかかるため、糸づくりの時期になると、子どもからおばあちゃんまで、いつでもどこへでも、麻の繊維を手に巻き、出かけていきます。


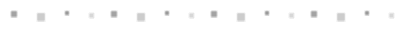





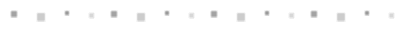
 ベトナムの黒モン族やタイの青モン族の人たちは、藍染めした布をつかって、自分たちの民族衣装や赤ちゃんの負ぶい紐やねんねこなどの生活に必要なものをつくります。
ベトナムの黒モン族やタイの青モン族の人たちは、藍染めした布をつかって、自分たちの民族衣装や赤ちゃんの負ぶい紐やねんねこなどの生活に必要なものをつくります。

 ろうけつ染めは、インドネシアではバティックと呼ばれ有名ですが、モン族のろうけつ染めも、手描きの文様に味があり、とてもすてきな布です。その藍染めをした文様の上やまわりに、赤い布などでアップリケすることがよくあります(写真上)。
ろうけつ染めは、インドネシアではバティックと呼ばれ有名ですが、モン族のろうけつ染めも、手描きの文様に味があり、とてもすてきな布です。その藍染めをした文様の上やまわりに、赤い布などでアップリケすることがよくあります(写真上)。


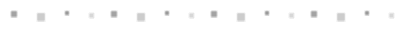

 泥藍の中に灰汁を入れ、溶かしていき、勢いよくかき回します。そして、時々かき回しながら1-2週間ほどすると、表面に青い泡が立ちはじめ、染められる状態になります。これを、「藍建て(あいだて)」といいます。
泥藍の中に灰汁を入れ、溶かしていき、勢いよくかき回します。そして、時々かき回しながら1-2週間ほどすると、表面に青い泡が立ちはじめ、染められる状態になります。これを、「藍建て(あいだて)」といいます。


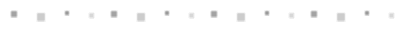
 黒モン族の人たちは、藍染めのピカピカの服を好みます。
黒モン族の人たちは、藍染めのピカピカの服を好みます。

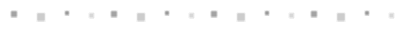

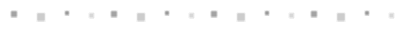
 織り人Topページへ
織り人Topページへ  モン族の民族伝統文化と刺繍ついて
モン族の民族伝統文化と刺繍ついて  ミェン族の民族伝統文化と刺繍について
ミェン族の民族伝統文化と刺繍について
 モン族クロスステッチ刺繍の商品一覧へ
モン族クロスステッチ刺繍の商品一覧へ  モン族リバースアップリケ商品一覧へ
モン族リバースアップリケ商品一覧へ  モン族ライフシーン刺繍商品一覧へ
モン族ライフシーン刺繍商品一覧へ
 ミェン族クロスステッチ刺繍の商品一覧へ
ミェン族クロスステッチ刺繍の商品一覧へ  カレン族手織り布の商品一覧へ
カレン族手織り布の商品一覧へ
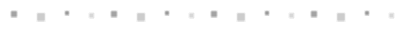

 商品のキズや色むらにつきましては、
商品のキズや色むらにつきましては、






